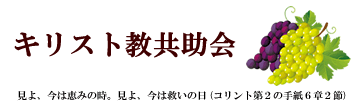【発題 2】キリスト教主義教育が持つ人格教育への希望― 私は何によって「私」になったのか ―新江(あらえ) 進
学校紹介
愛真高校は島根県にある私立の少人数全寮制普通科高校です。日々の学習や、食事作り・野菜作りなどの労働、沖縄などを訪問し現地の方と出会う平和学習を通して、「生きる」ということに焦点を当てた学びを大切にしています。教育目標としては、「確固たる良心と豊かな知性を合わせ備えた責任の主体たる独立人の育成」を掲げています。確かな良心と、豊かな知性、それらの土台となる、自身の生き方に責任を負う主体の芽生えを、学校の願いとしています。
はじめに
本来、経験も浅く、深い思慮もない私が語る資格はないことは重々承知しております。しかし、破ればかりの教員生活の中で、私がかろうじて指一本触れることが赦された「キリスト教主義教育が持つ人格教育への希望」について、私自身の個人的な経験から発題させていただきます。
まず始めに、9年前、私が教育実習の際に投げかけられた「問い」についてから、話を始めたいと思います。私は教育実習において、ある先生から、「あなたにとってキリスト教教育とは何か」と問われました。しかし、投げかけられた問いに対して、私が発することができたのは、「頭」で考えた言葉のみでした。私は、「キリスト教の精神で、生徒を愛する、大切にする」、そのように応えたことを覚えています。もちろん、それらのことは大切であることには間違いありません。しかし、私は、そこに生徒という人間の存在の重み、私という人間の弱さの自覚、そういったものを一切持たず、極めて表面的な言葉を発しました。おそらく、先生はそれをすぐに感じられたのだと思います。先生は、私の応答を否定されました。そして、答えに窮する私に対して、「これは宿題だな」とおっしゃいました。そして、その問いは、私の中で残り続け、現実の教員生活において、リアリティを持って再度私に問いかけてきました。
「私」からの逃亡
教員になってからしばらくして、私にとって決定的な挫折がありました。それは、ある生徒指導対応を決定する職員会議において、私が全く受け入れることができない結論に至った際の出来事でした。話し合いに多くの時間を費やしましたが、しかし最終的に、私は自分の思いを表現することを諦めました。私は自身の責任を放棄し、「みなさんがそう思うのであれば」と責任を他者になすりつけました。
私はここで、「職員会議の判断が間違っていた」と述べたいのではありません。しかし、この出来事は、私にとっては根本的な挫折でした。他者への恐怖から、大切にしたいと願っていた生徒への責任を放棄しました。それが、教育実習においては「生徒を愛する、大切にする」との言葉を発していた私の現実でした。しかし、私は、その姿を直視することはできませんでした。私は、ひたすらに、学校への絶望や憤りを発し、そんな自分自身を覆い隠していました。また、私は生徒への責任を放棄したと同時に、私の内にあった本当に私が大切にしていた「私」を手放し、踏みつぶしました。
そのような自己が分裂している状態を過ごす中で、身体の方は正直に悲鳴をあげ始めました。情緒が不安定になり、また、自律神経も不調をきたし常に発熱している状態となりました。私は、他者、生徒との関わりを極力避け、自分の姿を直視せず、じっと閉じこもるように自己を正当化しながら過ごしました。
自己欺瞞への限界
それから時を経て、私はクラス担任を受け持つこととなりました。しかし、その年は学校としての課題、問題、不安定さが一気に表出した年でもありました。私は、そのただ中で過ごしながら、結局の所、組織の不安定さのしわ寄せは、弱い立ち場の人の所へ集中することを目の当たりにしました。それはおそらく、国のような巨大な組織であっても、小さな組織であっても同じだと思います。学校という組織で、最も立場が弱い人とは生徒のことです。彼らが一番つらさ・苦しさを担っていました。私は職員として、問題に対し責任を持っていました。しかし、教職員集団の揺れのために生徒が苦しさを担う、その構造を知りながらも、私は自身が持つ責任を直視することを避けました。
そのような中で、私の中で芽生えた思いは、「キリスト教」愛真高等学校に、私が勤めていることへの違和感でした。「キリスト教」という名前のつく学校に、私のような人間が働く、それは、自分自身を欺きながらでなければできないことでした。表面上は「キリスト教教育」や「人間教育」を掲げながら教師をし、分厚い仮面を被りながら生きている私自身の姿に、私は引き裂かれるようなつらさを覚えました。そのつらさを無視しようとしても、また身体は正直に反応し、毎日嘔吐を繰り返しました。
そして、私は教師を辞める決意をしました。それは、自分の愚かさを直視した結果ではなく、むしろ見ることを避けるたの決断でした。この苦しさから逃げだすために教師を辞めたい、そしてさらには他者と関わることも辞めたいと願いました。誰とも関わらず、閉じた世界、家族の中だけは本当の自分を生き、それ以外の所ではキリスト教教育や人間教育などといった難しいことを一切考えず、仮面をつけて機械のように割り切って生きたい、そう心の底から思いました。
「私」への呼び掛け
そんな中、私にある知らせが届きました。それは、卒業生の1人が事故で亡くなったというものでした。その卒業生は、私が担任したクラスの1人でした。お別れ会の中では、保護者の方が、彼の人生を総括する言葉として、卒業感話を紹介してくださいました。愛真高校では、3年間の生活を振り返り自身の内面を卒業感話として言葉にし、全校生徒、保護者、職員を前にして語る場があります。本当に多くの人と関わった彼は、感謝の言葉を丁寧に述べた後に、こんな言葉を発しました。「ここ(愛真)で生活しながら考えを巡らせていました。そして確かに感じ取りました。『やっぱ、人間って面白いなぁ』ってことです。誰かの些細な言葉で傷つき、迷いながらも向き合って行く。人と人がぶつかり合って、高め合っていく姿。やっぱり、まだ僕には人間を辞められそうにないです。」
ここでいう「人間」とは単なる肉体のことではなく、人間を人間たらしめるものについて彼は述べていると私は感じました。「人間」として生きようともがいた彼の愛真高校での生活が鮮明に思い起こされた一方で、「人間」として生きるということを諦めようとしている私の姿を浮き彫りにしました。そして、そこには殻に閉じこもろうとする私を、彼が引き上げてくれるような感覚がありました。私は、最後の最後に、もう一度教師を辞めるかどうかを自身に問おうと、決意しました。私は丁度、校務分掌で校内の研修委員であったため、職員修養会を私自身が自らを問う最後の場として計画に関わりました。
「私」との対面と祈り
職員修養会当日、私の心には未だ「教師を辞めたい」という思いが確かに、大きくありました。しかし、そんな私の心を、一気に更地へと変えてくださったのは、開会礼拝での学校長の姿でした。学校長という組織の長が、揺れに揺れている学校の問題を目の前にして、涙を流しながら、ありのままの自分の姿を
語ってくださいました。それまでの自分の選択に全責任を担い、神に対して頭を下げる、その姿に直面し、その方の最も深い所にあるもの、まさに「人格」に触れた思いがしました。
また、そこで語られる一つ一つの「破れ」はまさに私の中にも確かに内在するものでした。また、学校長のその姿勢は、今まで決して見ようとしてこなかった私自身を優しく照らし出し、いざなわれるようにして、私は「私自身」に対面しました。
生徒ではなく自分を守ってきた言葉に尽くしがたい愚かさ、汚さ、情けなさ、今まで決して見ないようにしてきた私自身が、私に迫ってきました。私はそんな自分を自然と受け入れました。そして、その中で、私ができたことは、ただ祈ることだけでした。その祈りとは、赦しを求める祈りです。滅ぶべきこの身の赦しを、神にすがる祈りです。それは、私に最後に残された手段として、涙と共に、私の内から自然と出てきたものでした。
そして、私の祈りへの応答として私の内に示されたのは、「私はあなたを赦す」という聖書を貫くメッセージでした。そこに自分の全体重をかける、私はその感覚を初めて味わいました。その瞬間に「教師を辞める」という思いが一切吹き飛び、私の心が遙か先まで真っ平らになった感覚を覚えました。そして、その更地となった私の心には、確かに「私自身」がいました。破れも全て抱いてありのままの私として立つ、命の主体として立つ「私」がいました。
そして、赦しの中で生かされている「私」を心に刻んだとき、赦されているから何でも良いというような無責任な態度ではなく、そんな固有の人格を持つ私が、現実に対してどう応答していくのかが問われていることを深く感じました。現実問題は、変わらず山積みでした。しかし、以前と違うのは、そこで生きる生徒から目を背けるのでは無く、そこに「私」自身が対面し応答したい、そんな願いが自分の内から生まれていました。そして、まず心に浮かんだのは、生徒に謝りたいとの思いでした。私自身のこれまでの愚かさについて、逃げようとしてきた弱さについて、正直に自分自身を語り、誠実に謝ること、それが「私」として彼らの前に立ったとき、「しなければならない」ではなく、「したい」と心から自然と湧いてきたことでした。
そして、夏休み明け一番始めのHR、私はできるだけ無防備な私自身の言葉を語り、謝りました。生徒は、静寂の中、じっと、確かに、耳を傾けてくれました。綺麗事ではすまない本当に様々な思いを持ちながら生徒は聞いていたと思います。しかし、私は、確かに同じ人間としての「関わり」が生じたことを感覚として捉えました。それは、今までのことが無しになるとかではない、むしろその破れも全て抱きかかえた関係性が始まったことを感じました。
それからも多くの挫折や失敗はありました。しかし、私が今も教員を続けているのは、赦しの中で生かされ、応答していくという本来の「私」を経験したからに他なりません。
キリスト教主義教育が持つ人格教育への希望
今、改めて教育実習で問われた問い、「キリスト教教育とは何か」が私の中にリアリティを持って迫ってきます。今、その問いの前に立つ時、私の胸には「破れ果てた教師が、その破れ全てを抱えながら『私』を生きることが赦されている、その赦しの只中を生きること、それがキリスト教主義教育の命なのだ」との思いが浮かんできます。そして、そんな教員集団が生徒との現実に対して応答していく、その営みこそが、キリスト教主義教育なのだと思います。
そして、キリスト教主義教育は人格教育への確かな希望を持っていると私は感じます。「人は何によって『人格』となるのか」、このシンポジウムの主題に応答するならば、私の内からは「人は、他者の人格によって照らし出され、呼び起こされる」、そんな思いが湧いてきます。他者の人格とは、本当のありのままの他者の姿です。本来ならば隠したくて仕方が無い、頭を垂れ、赦しを請うしかない姿、そんな全てを抱きかかえた「その人自身」です。自身の鎧を脱いで出会いに来てくださる、そんな他者の「人格」に照らし出され、「私」が呼び起こされる。それは、私の経験に刻まれた、人格教育の一つの原石です。
「私」を喪失した子どもが増えた、と言われて久しいこの頃です。私自身、「私」を喪失した世代であると自覚しています。私は自分を押し殺しながら育ちました。小中学ではいじめがあり、私は被害者にも加害者にもなり、他者の顔色に脅えることを徹底して生き方に刻まれました。また、ゲームやネットなどの仮想世界は、「私」からの乖離に拍車をかけました。そして、自分というものが曖昧な中では人生そのものへの虚無感を感じ、そしてその虚無を埋めるための刹那的な興奮、そういうものを求めるように過ごしました。私は、現代の子どもが抱えているものを共感できるように思います。そんな子どもの奥底に潜む、その子自身の「人格」に差し込む光は何か、私ができることは何か。それは、彼らに何かをしようとする以前に、私が「私自身」を生きることだと思います。それがすぐに何か彼らに届くわけでもありませんし、何もないかもしれない。人格への目覚めは人の力の及ばない領域です。しかし、おそらくそこに立ち続けるしか、子どもの奥底に届くものはないのではないかと思います。
一方で、それは非常に苦しく難しいものであることも、同時に私は今突きつけられています。現実の泥沼の中で、もう立てなくなってしまう、また虚無の中にひきずり込まれてしまうこともあります。それは先程述べた職員修養会を経てから何度もありました。しかし、その度に、私は他者によって引き上げられました。1人では決して立てません。本当にお互いの破れを分かち合う大人同士の本当の意味での共同性が必要です。そんな教職員集団が、生徒との現実関係に応答していく、そこにキリスト教教育が持つ人格教育への確かな希望があります。
そしてこの言葉を発すると同時に、私は、同僚に、生徒に、自らの殻から出て、出会いに行っているのか、自分の城に安住しているだけではないのか、「私」を生きているのか、そう問われ続けています。 (キリスト教愛真高等学校教師)