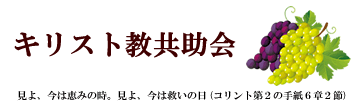歴史を顧みることは自分を切り裂くこと(2001年2月/3月) 清水 武彦
標題の言葉は、昨秋の京阪神修養会の主題講演者であった土肥昭夫先生が、佐伯勲先生の「戦時中の日本の教会はなぜ預言者的抵抗が出来なかったのか」という問いに対して述べられた言葉の一節である。先生は「日本のキリスト教は腰が弱いが、私自身弱い人間だから責められない。なぜ出来なかったのか、深層心理の問題として追求したい。戦時下の歴史を顧みることは自分を切り裂いているのですが、出来ることをやっていきたい」と述懐された。
2000年の大晦日の夜、京都では時ならぬ大文字五山の送り火が燃えた。若者たちの「20世紀の戦争と革命で死んだ多くの霊魂を慰めたい」という思いが契機になったという。この送り火は一向一揆から洛中を守るために起こった法華一揆に所縁があるという。法華一揆は1532年から5年間、洛中を民衆の手で支配した。送り火などお盆の行事に接すると、ヨーロッパの宗教改革と同じ頃、日本でも起こった宗教戟争をくぐり抜けて来た浄土真宗や法華宗の文化が民衆の生活に溶け込んで、今なお日本人の深層心理の一部を形成していることを感じさせられる。
20世紀の後半の日本で、キリスト者の言動は、新憲法の平和・人権・民主主義の先兵として進歩派に支持されて来たが、未だ日本人の深層心理に食い込むには至っていない。冷戦の集結と経済のグローバリズムによる世界情勢の激変とともに、日本社会には新保守主義が急速に広がって来ている。国民の間には戦後民主主義の中で閉息させられてきた民族主義的心情のマグマが吐け口を求めて鬱積し、それが右傾化政策を容認する層を構成している。
世界的な価値観喪失の時代の中で、物質文明の空しさを知った日本人は、とりわけ精神的支柱を求めて彷徨している。しかし、私たちは再び誤った民族主義や強権政治の道を選択することを容認してはならない。
イエスは「牧人のない羊のような群衆に対して腸のちぎれる想いに駆られ」て群衆の中に立ち給うた(マルコ6・34、岩波版)。私たちは今こそ日本人の深層心理と苦闘した先人の歴史を「自分を切り裂く」痛みをもって顧み、日本民衆の深層心理に、生きた命の言葉を語りかけねばならない。